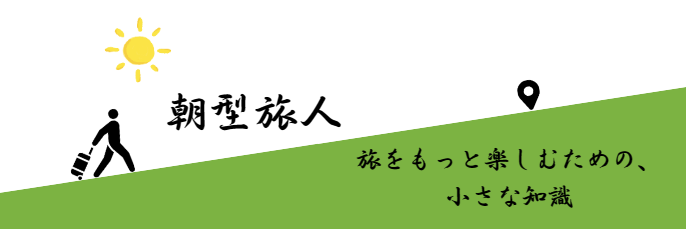【地域のストーリーを日本遺産として捉える】
こんにちは、朝型旅人です!
この記事では「教育遺産群」に息づく歴史や文化、そこに込められた“物語”を、日本遺産の視点からわかりやすく紹介します。
読み終わるころには、ただの観光や知識ではなく、「教育遺産群」という地域の奥深い魅力にきっと惹きこまれているはずです。
📚観光地としての教育遺産群📚
今回ご紹介する教育遺産群は、茨城県・栃木県・岡山県・大分県の4県にまたがるシリアル型の日本遺産です。複数の場所に分かれてて、観光地として紹介しにくいんですよ笑。
そこで今回は、その中でも特に有名な足利学校を紹介しておきます。

足利学校は日本最古の学校として知られ、栃木県にあります。この学校が質の高い教育を提供したおかげで、現在の日本の高い識字率にもつながってるんですね。
現在は復元された校舎や孔子廟が一般公開されており、落ち着いた庭園や書院の中で、当時の学びの空気を体感できます。
歴史的建造物巡りはもちろん、地方の町並みを歩きながら、学問にまつわるストーリーにも触れられるのが魅力です。修学旅行のコースにもぴったりでしょう。
📚教育遺産群の日本遺産ストーリー📚
とりあえず主要構成資産を紹介。
- 旧足利学校(栃木県。日本最古)
- 旧閑谷学校(岡山県。最古の庶民校)
- 咸宜園跡(大分県。かんぎえん。自由な私塾)
- 旧弘道館(茨城県。藩校の最高峰)
- 偕楽園(茨城県。かいらくえん。学びの休憩)
他にも登録されている文化財はありますが、この5つが印象的ですかね。
色々建物はありますが共通して言えるのは、
教育関連、さらに突き詰めればただの教育関連群ではなく、
人格教育も学ぶことができたということです。
「読み・書き・そろばん」以外に、礼節・人間形成・社会的責任みたいな人格教育も重視されてんですよ。英才教育を施してますね。
この教育遺産群の何がすごいかというと、身分の差を超えて誰もが教育を受けられたことです。単なる古い建物ではありません。
単に「学力」ではなく「人間力」を育てる。
偏差値至上主義になりかけている今の世の中にも教えてあげたい教育の本質です。
近世日本の教育こそが日本近代化の知的準備をした
―英社会学者ロナルド・ドーア―
現在でも、当時の教育を実際に受け、学ぶことができるところが何か所もあります。
現代までも続いている日本遺産のストーリーです。
学校は、いつまで経っても”学び舎”ですね。

似ている世界遺産
今回私が着目したのが人格教育です。ただ学力を上げるための施設ではなく、一人の人間として成長させることがこの遺産の本質であると考えたからです。

それを踏まえて、私が似ていると考えた世界遺産はイギリスにある「ニュー・ラナーク」です。
まぁ知っている方はほぼいないでしょう。特徴はこちら。
- 労働者のための施設が並ぶ村
- 綿糸の大量生産を行い、綿紡績業がメイン
- 人道主義のロバート・オーウェンが大活躍
…なんか、情報が増えたような、増えなかったような漠然とした説明ですよね笑。
「ニュー・ラナーク」は、産業革命期に誕生した理想的な工場村でありながら、教育と福祉を重視した社会改革の象徴として知られてるんですよ。
ここを世界遺産たる地位まで押し上げたのがオーウェンさん。世界史を受講した方なら知っているかも。あれです、空想的社会主義者。
この人は、工場の隣に幼児学校や夜間学校を設けたりして、労働者の子どもたちや大人たちに対し、単なる知識教育にとどまらず、道徳や礼儀を教えることを重視してたんですよ。
まさに「人格を育む教育」。それを体現したのがオーウェンさんってことです。
これって、「近世日本の教育遺産群」が伝える理念と共通していますよね。
日本とイギリス、文化も時代背景も異なる両者ですが、いずれも「教育は人を育て、社会を変える力を持つ」という信念を軸にしていた点は共通してるんですよ。
それが私が似ていると感じた理由でした。
まとめ
今回紹介した「近世日本の教育遺産群」は、ただの古い建物が集まっているわけじゃないんです。
ここには「学ぶこと」を通して、人として成長し、社会をよくしようっていう思いがしっかり詰まっているんですね。
そんな視点で見ると、歴史も旅ももっと楽しく、深くなるはず。
みなさんもぜひ、これらの「学び舎」を訪れて、
昔の人たちが大切にしてきた教育の心に触れてみてください。
新しい発見があるかもしれませんよ。
ここまでご覧いただきありがとうございました。またおいでくだされ。