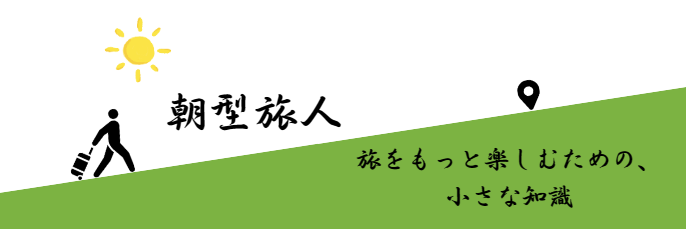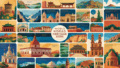【観光地を世界遺産として楽しむ】
こんにちは、朝型旅人です!
この記事では「知床」の見どころと、世界遺産としての価値をわかりやすく解説!
読み終わるころには、ただの観光地じゃない「知床」の魅力にハマっているはずです。
♻ 観光地としての知床 ♻

ささ、日本に5件しかないレアな自然遺産の一角、知床についての記事ですよ!
まぁだから何かが変わるってわけではありませんが。
知床半島は北海道東端、オホーツク海に突き出すように広がっている自然の宝庫です。
「日本最果ての地」と呼ばれるだけあってアクセスはお世辞にもいいとは言えませんね。
女満別空港から車で約2時間
JR釧網本線「知床斜里駅」からバスで約50分
なんなら冬季は道路が閉鎖されている恐れもあります。あな恐ろしや。
それでも行く価値があるのが知床なんです。
なんといっても「流氷」。日本で流氷がみられるのはここ知床だけ。もうこれだけで行く価値ありますね。しかも流氷ウォークも行っていて海の上に立つという非日常体験を味わうことができます。
ほかにも
- 原生林の中にある知床五湖
- ドライブ最適知床峠(知床横断道路)
- 温泉が流れるカムイワッカ湯の滝
- 野生動物と遭遇できる
など見所は多数。北海道なのでグルメも100点。
……お腹空いてきた。

♻ 世界遺産としての知床 ♻
知床は2005年に自然遺産として登録された世界遺産です。
知床の登録基準はⅸ、ⅹ。簡単に言うと
- 海、陸、川の相互作用のある生態系の顕著な見本だね!
- 多彩な自然環境で生物多様性の生育・生息域を内包してるね!
ってことですね。別に日本で唯一流氷を見ることができるから世界遺産になったわけではないってことです。流氷も観光名所としては素晴らしいんだけどね。
世界遺産としての知床の特徴は以下の通り。
西と東で別世界!知床の二つの顔
知床と一言にいっても「西側のウトロ」と「東側の羅臼(らうす)」では環境が全然違います。
| 比較項目 | ウトロ(西側) | 羅臼(東側) |
|---|---|---|
| 主な特徴 | 陸の絶景エリア | 海の命が主役のエリア |
| 主要産業 | 観光業 | 漁業 |
| 野生動物 | ヒグマ、キタキツネなど | シャチ、クジラなど |
| おすすめの楽しみ方 | トレッキングや断崖クルーズ | 海洋動物観察、流氷とシャチ |
| 雰囲気 | ダイナミックで観光地らしい | ローカルな港町の雰囲気 |
| アクセス | 女満別空港→斜里経由で 約2時間 | 中標津空港または釧路空港 →車で約2時間 |
他にも降水量や気温、地形などが異なっています。
おすすめは春~夏はウトロ側、冬は羅臼側の観光。
なんだか観光地としての説明な気もしますが、この二面性こそが生物多様性を生み出している秘訣なのです。
ヒグマもシャチも”神様”。神様と暮らすアイヌの共生
知床では、ヒグマも、シャチも、シマフクロウも――みんな“神様”。
そう考えていたのが、この地に古くから暮らしてきたアイヌの人々。自然の中の動物や植物、風や火、水にまで「カムイ(神)」が宿ると信じ、共に生きてきた民族です。
なんか日本の「八百万の神」の概念と通じるところがありますね。
アイヌの人々の特徴は「自然と共生した狩猟採集文化」です。動物の捕獲というより、恵みをいただくという感覚。自然に感謝を忘れない文化でした。
このような「神様と共にある生き方」によって知床は長い間手つかずの自然を保たれていたのです。
やっぱ自然は、人間の都合で形を変えるものではなくて”共に在る”ものかもしれませんねぇ。

画像はアイヌの人々が「カムイトー=神の湖」と呼んでいて、今も立ち入りが制限されている摩周湖。手つかずの自然を維持しています。
……やっぱり人間の手が加わらない方が良いこともあるよな~。
流氷が来るとヒグマが喜ぶ?”動く世界遺産”である理由
果たしてこんな因果関係が成り立つのでしょうか?流氷→ヒグマだなんて。
実は世界遺産・知床の大きな特徴はこの豊かな食物連鎖を観測することができる点です!
こちらで知床の食物連鎖を確認できます。
知床の食物連鎖の凄いところは海から陸への連なる生態系がみられるという点です。
流氷の到来
↓
植物プランクトンの増殖
↓
動物プランクトン
↓
小魚・貝類
↓
シャチ・アザラシ・ヒグマ etc.
つまり、海から森へ、命がつながっていくこの仕組みこそが、知床が“動く世界遺産”たる所以ってことですね。
まとめ
流氷などのダイナミックな自然やアイヌの人々の自然との共生、動き続ける生態系ーー
どれをとっても「生きた世界遺産」ですね。
絶景が「きれい」で終わらない。
命のつながりや自然のリズムが、静かに胸に残る。
知床は、そんな“生きた世界遺産”ってな印象を受けました。
人間の創出する文化遺産とはまた違う良さがありました。
ここまでご覧いただきありがとうございました。またおいでくだされ。