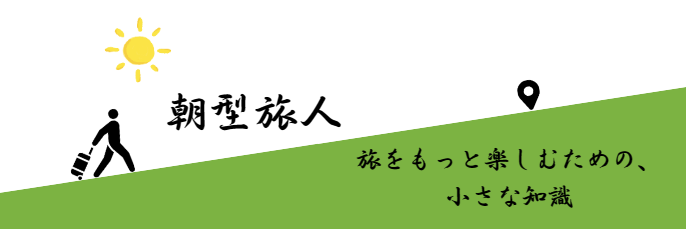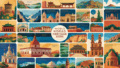【地域のストーリーを日本遺産として捉える】
こんにちは、朝型旅人です!
この記事では「伊賀・甲賀」に息づく歴史や文化、そこに込められた“物語”を、日本遺産の視点からわかりやすく紹介します。
読み終わるころには、ただの観光や知識ではなく、「伊賀・甲賀」という地域の奥深い魅力にきっと惹きこまれているはずです。
🥷観光地としての伊賀・甲賀🥷

日本遺産について詳しくない方でも「忍者=伊賀とか甲賀の地域の人」みたいな認識があると思います。
「服部半蔵(はっとり はんぞう)」とか「石川五右衛門(いしかわ ごえもん)」とか聞いたことがあるんじゃないでしょうか。彼らは伊賀の忍者という説が有力です。
近世以降の軍記とか小説とかの影響で「伊賀・甲賀=忍者」みたいな認識が広まったんです。まぁ伊賀・甲賀が観光地化を推し進めているなど理由は他にもありますが。
伊賀があるのは三重県伊賀市。「伊賀流忍者博物館」では、忍者が忍者屋敷のからくりを教えてくれたり、手裏剣を投げる(打つ)体験もできます。伊賀流忍者博物館(公式サイト)
甲賀があるのは滋賀県甲賀市。「甲賀流忍術屋敷」では実際の甲賀流忍者が住んでいた家を見学できたり、忍者飲用薬草茶(健保茶)試飲ができたりします。甲賀流忍術屋敷(公式サイト)
どちらも「忍者」をその地域の特徴として強く押し出していますね。
🥷伊賀・甲賀の日本遺産ストーリー🥷
まず、伊賀・甲賀の日本遺産名は「忍びの里 伊賀・甲賀」です。かっこいい名前ですね。そこらのキラキラネームよりかっこいい。
伊賀・甲賀は場所が離れていますが、忍びが多く存在したところっていう共通点で日本遺産に登録されているんですね。
伊賀・甲賀に忍者が多くなったのには理由があります。
それは「京都・安土」に近いから。安土は現在の滋賀県。
都に近いってことはその時代の潮流を理解しやすいし、有力者が亡命しやすいんですよね。
有力者が命からがら逃げてくるからならその人を守る人が出てきます。それが忍者です。ちなみに忍者が多く活躍したのは戦国時代(15~16世紀)。
有名なのは「神君伊賀越え」です。
簡単に説明すると、1582年、本能寺の変直後の出来事。命を狙われた徳川家康が堺(大阪)から三河(愛知)までを最短ルートで逃げ帰るっていう伝説的エピソードです。
ちなみに「神君」ってのは神の如き君主=家康を表します。
その神君伊賀越えで家康を護衛したのが伊賀者・甲賀者です。服部半蔵もこのときに活躍しました。
手裏剣よりもこっちの方が忍びっぽいなって感じます。いかにも隠密行動みたいな……ね?
このような「戦うのではなく逃げる」ってのが忍者で専売特許です。その代表格が忍者屋敷。回転壁や隠し階段、下見窓などのカラクリはあくまでも逃げるためのもの。
大切なものは、目に見えないんだよ
――――サン=テグジュペリ『星の王子さま(Le Petit Prince)』
まさにこれですね。
似ている世界遺産
これまでの説明で忍者は逃げるのに特化している、忍者屋敷などではそのための工夫がみられるってことが分かりました。
じゃあこの日本遺残と似ている世界遺産は何なのか。
私は「アルベロベッロのトゥルッリ(イタリア)」を推します。「アルベロベッロのトゥルッリ」の特徴は以下の通り。
- 特徴的な屋根をもつ住居
- 石灰石を用いた建物でモルタル不使用
- 一つの部屋に一つの屋根がついている
- レゴブロックみたいに石積みしてできている
- 今も人が住んでいる現役の住居

一見何の変哲もない、かわいらしい家ですよね?
まぁ自分の第一印象は「名前面白いな笑」でしたが。
実はこの「アルベロベッロのトゥルッリ」、重税を避けるためにいつでも壊せるように作られているんです。ほら、石造りだから壊しやすいし、レゴブロックみたいなんで再建しやすいし。
しかも部屋ごとに屋根がついているから部分的に取り崩すのも可。
普段は普通に生活しておいて、税の監査が来たら家を壊して税の支払いを避ける。
表面的には分からない裏の戦略が光る遺産という点で似ていますね。
しかも何が凄いってどちらの遺産も地域全体でやっていること。一人の賢人だけが行ったのではなく、地域の共同体として行い、文化として成立しているってのもすごいですね。
まとめ
伊賀や甲賀を訪れると、手裏剣やからくり屋敷、忍者体験など、わくわくする観光が目の前に広がります。
でもその奥には、地域の人々が築いた知恵と暮らしの防衛術、そして文化として受け継がれてきたストーリーがあります。
日本遺産「忍びの里 伊賀・甲賀」は、そんな“表に見えない価値”を伝える場所でもあるのです。伊賀・甲賀を訪れる機会があれば、その価値にも触れてみてください。
きっと、旅の記憶がより深く、より印象的なものになるはずです。
ここまでご覧いただきありがとうございました。またおいでくだされ。