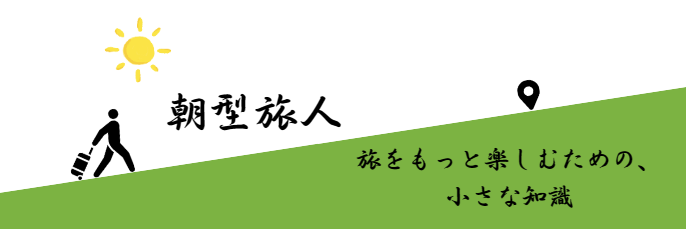【観光地を世界遺産として楽しむ】
こんにちは、朝型旅人です!
この記事では「古都奈良の文化財」の見どころと、世界遺産としての価値をわかりやすく解説!
読み終わるころには、ただの観光地じゃない「古都奈良の文化財」の魅力にハマっているはずです。
🦌 観光地としての奈良 🦌

「奈良」と聞いて、何を思い浮かべますか?
ま、鹿でしょう。自分はもう奈良=鹿ですね。他にもいいところがたくさんあるのは分かりますが。
んでもって鹿といったら奈良公園ですね。
もっと言えば奈良公園といったら修学旅行ですね笑。
修学旅行で行くところ、そこが古都奈良の世界遺産と思ってもらって構いません。
実際には構成資産の大半が修学旅行コースに含まれてます。
ちゃんとした範囲はあとで説明しますので。
特に観光地化している三か所(朝型旅人の独断と偏見で選好)を抜粋して紹介しときます。
まずは東大寺。世界最大級の木造建築である大仏殿があります。よく奈良の大仏って言われているあれのことですね。
桜や紅葉との相性が良く、景観も優れています。そんで法華堂とか南大門とかもあるんですよ。これだけで一つの世界遺産になり得るパワーのある場所だと思っています。
次は春日大社。東大寺からほど近く、セットで観光するのがおすすめ。朱色の社殿と苔むす参道が特徴的。鹿さんも歩いていて、なんというか、奈良らしい。
最後は薬師寺。薬師寺は東大寺からは離れています。東塔と西塔という2つの国宝が左右対称で建っているのが特徴。薬師如来が本尊なので、健康や癒しを求めている人はぜひここに。
ほかにも様々な寺社が残っていてそれぞれ一見の価値がある建造物です。
だからこそ世界遺産になっているんですけどね。

以下で世界遺産としての「古都奈良の文化財」を紐解いていきます。
🦌 世界遺産としての奈良 🦌
まずはですね、古都奈良の文化財の全貌から紹介します。この世界遺産は合計8つの構成遺産から成り立っている文化遺産です。その8つとは、
- 元興寺
- 興福寺
- 薬師寺
- 春日大社
- 春日山原始林
- 平城宮跡
- 唐招提寺
- 東大寺
です。どれも聞いたことはあるのではないでしょうか。
登録基準はⅱ、ⅲ、ⅳ、ⅵで、ざっくり説明すると
- 日本の木造建築技術が光ってるし、日韓中の文化的交流が示されているね!
- 平城宮跡は失われた考古学的遺跡として価値が高いね!
- 奈良時代の日本の寺院建築様式をよくとどめているね!
- 春日山原始林は日本独特の神道思想を示しているね!
こんな感じですかね。8つも遺産があるからか、幅広く登録基準をカバーできていますね。
今回取り上げる世界遺産としての古都奈良の文化財の特徴は、
です。ほんじゃ一つっつ見ていきましょう。
「文化財」なのに建物じゃない!なんで自然が?
「古都奈良の文化財」の構成遺産の中で唯一建物じゃない遺産、春日山原始林。
これは名前の通り、山(自然)です。
これだけで少し疑問を感じた人は世界遺産検定1級レベルの素質あると思います。
……自然が入っているのに複合遺産じゃないの?と。
春日山原始林はあくまで文化遺産として登録されているんです。
理由は山(あるいは森)自体が神聖化されていて信仰されていたから。
自然を信仰するって日本の神道思想を表しているものとして結構評価良いんですよね。
これは神道の「八百万の神」に由来します。
ちなみに「厳島神社」にある弥山(みせん)も同じ理由で高く評価されています。
そもそもなんで寺が密集しているの?

「古都奈良の文化財」で8つの遺産が狭い地域に密集していますが、お寺がいっぱいありますよね。疑問に思いませんか?こんなに寺いる?
当時は必要だった理由があるんです。ざっくり二つ。
一つ目は権力や勢力の象徴ですね。8世紀ごろの日本では寺院は宗教施設としてではなく、政治権力や貴族勢力の象徴だったんです。
俺、強いよ?ってことでいっぱいお寺作ったんですね。
要は強いマウントです。
このマウントの取り合いのおかげで世界遺産が生まれたのでマウントも悪いことじゃないかもしれないですね。
二つ目は神仏習合の過程でっす。奈良は仏教と神道が融合する過程で、同じ時期に複数の信仰施設が共存しました。これも密集の一因ですね。
つまり、奈良のお寺はマウント合戦、神仏習合のおかげで密集したんですね。まぁ密集してくれたおかげで奈良の寺院群は「文化的景観」として完成度が高くなったんですよね。
観光地を世界遺産として捉える1300年祭
構成遺産の一つ、平城宮跡ってのがあります。
一応中学校でも習いましたね。
「なんと(710)立派な平城京」ってやつです。
ってことはですよ。2025年現在は平城京に遷都してから1315年ですね。
実は遷都1300年(西暦2010年)の時に「平城京遷都1300年祭」ってのが行われました。
もうとっくのとうに終わっちゃってるんですけど、このイベントは「観光地を世界遺産として捉える」好例だったと思っています。
1300年祭で実際に行われたことはこちら
- 第一次大極殿の復元公開(中にも入ることができた)
- 遣唐使船の復元展示(原寸大)
- 薬師寺、唐招提寺などで特別展示やライトアップ
これは世界遺産の今では見ることのできない価値を可視化して、奈良全体で「観光地を世界遺産として捉える」を実現したすんごく良いイベントでした。
実際に来場者数は当初予定していた1.5倍のおよそ363万人。来場者消費額は約967億円と集計されていて、大成功を収めました。数値は第2回中間報告から抜粋。
しかもこの祭り、すごいのは祭りのあとです。
2010年に開催された1300年祭。2011年には仮設施設の撤去が行われました。
奈良を訪れる人も一気に減少し、以前のような「静かな史跡」に戻りました。
そのまま観光地丸出しにするのもいいけど即座に撤去して元の世界遺産の風貌に戻る。
これ、結構好きです。
世界遺産ってこういうのがいいとおもうんですよね。
まとめ
奈良といえば「鹿とか大仏」
――そう思っている人にこそ、「古都奈良の文化財」はぜひ深掘りしてもらいたい世界遺産です。
建物だけでなく、自然そのものが信仰の対象だった点。
お寺が密集した裏には、権力や信仰が入り混じった歴史がある点。
さらには、1300年の節目に一度“派手に”魅せた上で、また静けさに戻るような世界遺産としての矜持があった点。
こんなこと、観光ガイドには載ってませんもんね。
ただ見るだけの観光地ではなく、知って・感じることで何倍も深く味わえる場所――それがこの「古都奈良の文化財」なんでしょうね。
ここまでご覧いただきありがとうございました。またおいでくだされ。