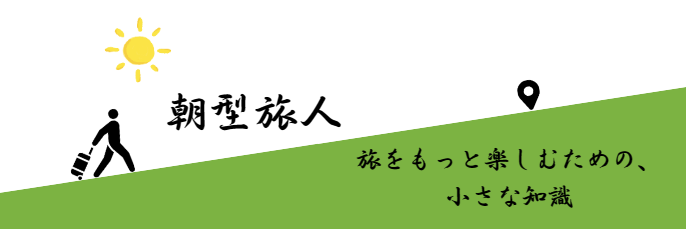【地域のストーリーを日本遺産として捉える】
こんにちは、朝型旅人です!
この記事では「行田」に息づく歴史や文化、そこに込められた“物語”を、日本遺産の視点からわかりやすく紹介します。
読み終わるころには、ただの観光や知識ではなく、「行田」という地域の奥深い魅力にきっと惹きこまれているはずです。
👣観光地としての行田👣
今回紹介するのは、埼玉県北部に位置する行田市。「ぎょうだし」って言います。
熊谷駅からバス、車で20分ほどで行くことのできる場所ですね。アクセスは悪くない。
この場所の有名なところは、忍城(おしじょう)と足袋(たび)ですね。
足袋についてはあとで説明するのでここは忍城について簡単に。
忍城ってのは戦国期の名城で、異名は”浮き城”。かっこいいですね。
城の周囲を川や沼に囲まれているのが”浮き城”の由来。

周囲を見ずに囲まれているのって城の機能としてめっちゃ良いんですよ。
特に有名なのは1590年の豊臣秀吉による小田原攻めですね。
石田三成が水攻めを行ったのに、城が沈まなかったって出来事。
現在は模擬天守が再建され、歴史公園として整備されているので気軽に立ち寄ることができますよ。
ちなみにここは映画『のぼうの城』の舞台にもなったところです。
歴史ファンはぜひ。
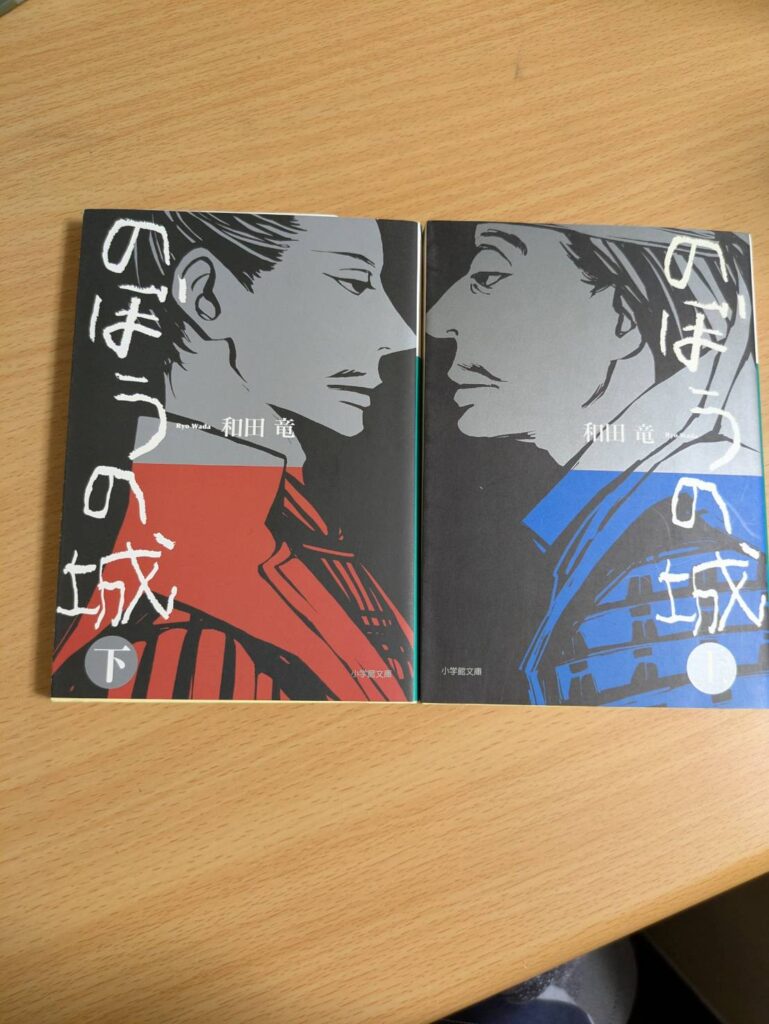
上下巻ですが、割と短めなので手軽に読めました。
こんなシンボル的な存在、忍城があるのが行田市ですね。
観光地だけではなくて、ここは地元グルメも豊富にあります。
ゼリーフライとかフライとか。
…実はゼリーフライとフライって別物なんですよ笑。
ゼリーフライは、おからとジャガイモを使ったコロッケ。
フライは、小麦粉を水で溶いた生地を鉄板で焼いたもの。
歴史と食を堪能できて、なおかつアクセスもいい場所ってことですね。
👣行田の日本遺産ストーリー👣
この遺産の正式名は「和装文化の足元を支え続ける足袋のまち行田」です。
まぁ要は、「行田市は足袋が強いよ」ってことです。
行田市のみの登録なので地域型の日本遺産ですね。

今でこそ足袋を履いている人は見かけませんが、かつての和装には欠かせない存在だったんですよ。その足袋の一大生産地がここ行田だったと。
まずなんで行田で足袋作りが盛んになったんでしょう?
理由はいくつかあります。
一つ目は地理的条件。行田市は、利根川と荒川に囲まれてて、それの氾濫で運ばれてきた砂質の土が堆積してるんですよ。その土は、足袋を作るときに必要な布の晒しや染めに適してるんです。
さらに川が多い地域だから水も豊富。夏場は気温も高く、布を乾かすのにうってつけ。
あとは「交通の便利さ」ですかね。江戸に近い行田は、原料を運ぶにも製品を出荷するにもスムーズだったんです。これも重要なポイント。
二つ目は政治的条件。江戸時代、行田は「忍藩(おしはん)」の城下町として栄えてました。藩の中心は忍城。忍藩は足袋作りを地域の基幹産業と位置づけ、産業振興に積極的に取り組みました。
具体的には、技術を持つ職人を呼び寄せたり、取引を広げやすい環境を整えたり…
これらの条件が要因となって、行田の足袋は江戸時代から全国へと広まり、明治期には“足袋のまち”として大ブレイクする土台が築かれたわけですよ。
行田の足袋は、その品質の高さにも定評があるんですよ。他の場所(名古屋とか博多とか)でも足袋は作られてましたが、行田の足袋は丁寧な縫い上げ、履き心地の良さから全国シェアの約8割を占めてました。
…完全に独占企業ですね。
価格釣りあげたりしてもみんな買ってくれそう笑。
行田では現代でも職人による手縫いの足袋や、デザイン足袋など、新しい挑戦が続いています。実際に足袋作りを体験できる施設もあり、歴史を学べる資料館も残っています。
まさに「足袋のまち」ですね。
私が特に着目したのは「足袋蔵まちづくり」ってとこ。かつての工場跡や蔵を活用し、カフェやギャラリーとして再生する取り組みで、観光客が足袋文化の歴史を肌で感じられるようになってます。
また「きねや足袋」のように、伝統技術を現代に活かしたブランドもあり、ランニング専用の足袋型シューズは国内外から注目を集めています。スポーツと伝統の融合ってのが「今に生きる日本遺産」感あって良いですね。
こちらにリンク貼っときますので良ければぜひ。
足袋蔵まちづくりミュージアム(栗代蔵) | 観光スポット一覧 | 【公式】埼玉観光情報 – ちょこたび埼玉、NPO法人ぎょうだ足袋蔵ネットワーク
今では足袋文化自体が下火傾向にあって、行田市の全盛期には及びませんが、それでも足袋産業は続いています。理由は日本文化の舞台で多く用いられているから。
歌舞伎や能といった舞台で足袋が使われてるんですよ。
足袋を通じて、行田は「日本の伝統文化の裏方」として貢献してるんですね。
似ている世界遺産
行田市の特徴を踏まえて、私が似ていると感じた世界遺産はリヨンの歴史地区です。
フランスにある文化遺産。
まぁまずはリヨンの歴史地区の説明から。
- 絹織物産業に関する建造物が多く残っている
- フランス国内で最初にフランス語の本が出版された
- 小説『星の王子様』の作者、サン・テグジュペリの生まれ故郷
下二つは世界遺産検定1級を目指している人は覚えておきましょ。
なんだかんだ出ます。
こんな感じですかね。特に着目してほしいのが一つ目の「絹織物~」の箇所。
ここは絹織物産業が発展した場所なんですよ。そのうえ当時の建物も残ってて、2000年の歴史が残されてるという価値ある世界遺産です。
さて、リヨンと行田市。何が似ているのかというと「衣服文化を足元から支えた産業都市」ってとこです。
リヨンがヨーロッパの宮廷文化を「絹」で輝かせたのに対し、
行田は日本の伝統衣装である和装を「足袋」で陰ながら支えてきました。
単なる産業を超えて、人々の暮らしや文化の根幹にかかわった点で、似てますね。
さらに面白いのは、リヨンの絹も行田の足袋も「職人の技」に支えられていることです。機械に頼って生産を進めたのではなく、あくまでも手作業なんです。
どちらの都市も、表舞台で脚光を浴びる存在ではなくても、その裏で文化を支え続けたという意味で「縁の下の力持ち」存在ですね。
こういう場所を世界遺産とするのはすごく賛成。
もう少し広げて考えると、行田とリヨンは「今も残る職人のまち」という共通点もあります。リヨンでは織物体験や博物館で歴史を知ることができますし、行田でも足袋づくりの体験や資料館が残されています。観光客にとっても「ものづくりの歴史に触れる旅」ができる場所なんですね。
つまり、リヨンの街並みに職人の息遣いを感じるように、行田でも足袋文化を通じて日本の和装文化の奥深さを感じることができる。そんな共通点を意識しながら訪れると、行田の魅力がより一層深まるはずです。
まとめ
行田の足袋は、和装文化の縁の下の力持ち。
町中を歩けば、職人の技と歴史、そして地域の暮らしが同時に感じられます。
歴史と生活文化を一度に体感できる貴重な町――
足袋のまち行田で、和装文化の深さを感じてみましょ!
小さな旅の寄り道でも、きっと忘れられない発見が待っています。
ここまでご覧いただきありがとうございました。またおいでくだされ。