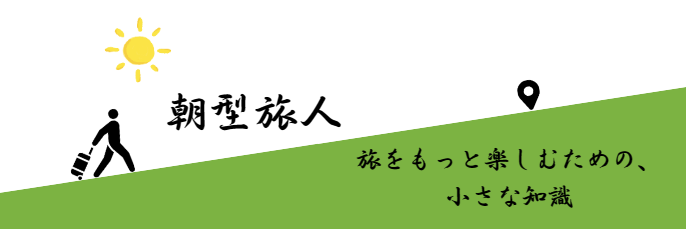【地域のストーリーを日本遺産として捉える】
こんにちは、朝型旅人です!
この記事では「峡東地域」に息づく歴史や文化、そこに込められた“物語”を、日本遺産の視点からわかりやすく紹介します。
読み終わるころには、ただの観光や知識ではなく、「峡東地域」という地域の奥深い魅力にきっと惹きこまれているはずです。
🍇 観光地としての峡東地域 🍇

まず場所の説明から。
峡東地域ってのは、山梨県の甲府盆地の東部に位置するエリアです。
具体的には甲州市(勝沼・塩山)、山梨市、笛吹市など。
この地域、実は「日本一のぶどうの産地」なんですよ。
盆地特有の気候と水はけの良い扇状地が、ぶどう栽培にとって絶好の環境なんですね。
観光の定番って言ったら勝沼のぶどう狩り体験ですね。あとは、ワイナリー巡りとか。有名な老舗から、個性派ワイナリーまで、趣向を凝らしたテイスティングが楽しめちゃいます。
最近ではカフェやギャラリーを併設したワイナリーも増えてます。
若い世代とかお酒弱い層にも観光を促していて良いですね。日本遺産のお手本ですね。
絶景もあります。ぶどう畑からの風景。
特に朝夕の時間帯には、ぶどう畑の向こうに、霧に包まれた山々が広がります。
まさに「風景そのものが旅の目的地」になる場所です。
🍇 峡東地域の日本遺産ストーリー 🍇

今回紹介する遺産、登録名は「葡萄畑が織りなす風景―山梨県峡東地域―」です。
名前の通り、ブドウ栽培のストーリーですね。
山梨県は今でこそ、甲州ぶどうなどで有名ですが、ブドウ栽培の初めは奈良時代の薬師如来です。
大善寺(ぶどう寺)の薬師如来が山梨県東部にブドウ栽培を伝えたとされています。
山梨のブドウ名産には主に2つのきっかけがありました。
1つは明治時代の殖産興業です。殖産興業とは産業を育成・推進する政策のこと。
ワインが殖産興業の対象になったことで、ブドウ生産が盛んな山梨で葡萄酒醸造所が開かれました。
2つ目は養蚕業の衰退です。これだけじゃ繋がりが意味不明ですね。
化学繊維の普及によって稼ぎを失った山梨の養蚕業者が、ブドウ栽培を始めたんです。
ブドウ栽培って収益性が高いから始めやすかったんですよね。
そんなこんなで山梨=ブドウの生産地として地位を確立してったんです。
山梨のぶどう畑は、ただの農地ではなく、
時代の転換点ごとに育まれた「生きたストーリー」ってことですね。
似ている世界遺産
普段は似ている世界遺産を考察するときは大まかな特徴が合致している複数の世界遺産を抽出してから、私なりに納得のいく遺産をあげているんですけど…
今回はこれ以上は差別化できない!一つに絞れないって感じでした。
長年ブドウ栽培が行われていて評価された世界遺産が8件もあるんですよ!
もうこれ以上は絞れないんで今回は8件紹介します。
- ブルゴーニュのブドウ栽培の景観(フランス)
- シャンパーニュの丘陵、醸造所と貯蔵庫(フランス)
- ラヴォー地域のブドウ畑(スイス)
- ピーコ島のブドウ栽培の景観(ポルトガル)
- アルト・ドウロのワイン生産地域(ポルトガル)
- トカイ地方のワイン産地の歴史的文化的景観(ハンガリー)
- ピエモンテのブドウ園の景観:ランゲ・ロエロとモンフェッラート(イタリア)
- コネリアーノとヴァルドッビアーデネのプロセッコ栽培丘陵群(イタリア)

これだけ色々書き連ねましたが、全部に共通してるのが、
「ぶどう畑が単なる農地ではなく、地域の歴史・文化を反映する景観である」という点です。
山梨の峡東地域も同様に、長い年月をかけて形成された景観と文化が、今もあるんですよ。
なのでもう似ているっていうか同じじゃないのとすら思っています。
もういっそのこと「日本のブドウ畑の景観:山梨県峡東地域」とかで世界遺産暫定リスト申請してみたらいいのに……
まとめ
世界には、ぶどう畑が世界遺産になっている地域がいくつもあります。
山梨・峡東地域もまた、それらに肩を並べるだけの文化と風景を持つ場所です。
「観光地」としてだけでなく、「日本遺産」として見つめることで、この土地の見え方がきっと変わるはずです。
早いうちに観光しておかないと、世界遺産に登録されたら出遅れちゃいますよ?笑。
ここまでご覧いただきありがとうございました。またおいでくだされ。