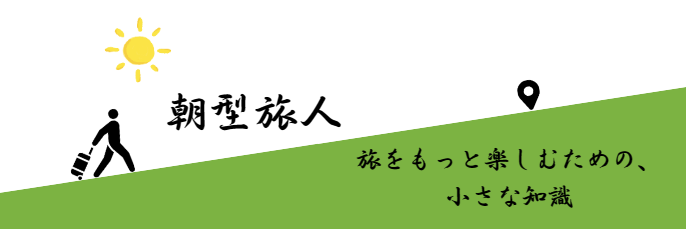【地域のストーリーを日本遺産として捉える】
こんにちは、朝型旅人です!
この記事では「くにさき」に息づく歴史や文化、そこに込められた“物語”を、日本遺産の視点からわかりやすく紹介します。
読み終わるころには、ただの観光や知識ではなく、「くにさき」という地域の奥深い魅力にきっと惹きこまれているはずです。
👹観光地としてのくにさき👹

648年に創建されてから13世紀以上も祀られている神聖な場所です。
まず、「くにさき」ってどこ?
私も詳しくは知りませんでした。
「くにさき」ってのは大分県にある国東半島(くにさきはんとう)です。
より詳細にすると豊後高田市、国東市あたり。
この辺の観光地としての紹介からしてきましょ。
国東半島は、大分県のなかでも、ちょっと突き出た三日月形のとこです。
最寄りは大分空港で、別府や湯布院からもアクセスできます。
国東半島の魅力は、なんといっても「海と山の距離が近い」こと。ドライブすれば、片側には青い海、もう片側には緑豊かな山が広がる、“日本の原風景”を一度に楽しめちゃいます。
海辺の漁港では新鮮な魚介が揚がり、内陸に入ると棚田や畑が連なる景観が広がってます。
また、半島をめぐる「国東半島サイクリングロード」も人気で、海風を感じながら走ると爽快感抜群。最近は、アートイベントとか古民家カフェとかも増えてきてて、「素朴さと発見」が同居してます。

美しい景観も相まって場違い感がすごい笑。
昭和の町・豊後高田市では、レトロな商店街を歩くことができます。
駄菓子屋、昔ながらの映画館など、SNS映えを狙えるノスタルジックな風景がいっぱい。
国東半島は農業も漁業も盛んです。
…これってどういうことかというと、グルメが強いんですよ。
山の幸・海の幸がどちらも楽しめる贅沢なエリアです。
特に「タコ飯」や「地ダコの唐揚げ」が名物。
観光地としては決して派手じゃないけど、自然好きな私からすればこの素朴さが良い…。
👹くにさきの日本遺産ストーリー👹
今回の国東半島、日本遺産登録名は「鬼が仏になった里『くにさき』」です。
なんかこんな内容の昔話ありそう。
登録範囲は大分県のみで、シリアル型の日本遺産ですね。
「くにさき」は国東半島のことを指しています。あえて「国東」と漢字にしないのはこの遺産の登録範囲が国東市だけじゃないからだと思っています。
ひらがなの方が物語感、民話感も出ますし笑。
そんじゃ遺産の本質について説明しましょう。
まず初めに。くにさきの鬼は畏怖の対象ではありませんでした。
これが他の地域の鬼と異なっているところ。
人々は鬼をあこがれの目線で見て、仏と重ねていたんです。
通常は鬼≠仏ですが、くにさきの人々は鬼=仏だったってことです。
この人間と鬼の関係性が日本遺産に選出された一因ですね。
鬼と仏が結びつくって、ちょっと違和感抱きますよね。でも日本文化を振り返ると「恐ろしいものを畏れながらも共存する」発想は意外とあるんですよ。
たとえば寺院の屋根にある鬼瓦。鬼の顔をした瓦を飾ることで魔を祓う意味を持ちます。
たとえば節分の豆まき。「鬼を追い払う」と同時に「鬼は内」と唱える地域も存在します。

観音様の前に鬼はいないって認識なんですって。
さらには「鬼子母神(きしもじん)」のように、かつては恐怖の対象だった鬼女が、最終的には安産や子育ての守護神に転じる信仰もあったりするんですよ。
つまり「恐ろしい存在をただ排除するのではなく、役割を与えて受け入れる」という日本人特有の感覚が、くにさきではとりわけ表現されたって解釈できますね。
くにさきには様々な仏教関連のイベント(これを法会といいます)があるんですけど、
最大のイベントは「修正鬼絵(しゅじょうおにえ)」です。
修正鬼絵は鬼に出会うことのできる夜のこと。鬼が松明をもって暴れまわり、人々の尻を打つ。
…なんかこれ聞くと鬼はやっぱ悪なのではって思いますが笑。
しかし、くにさきの人々はそうは思っていません。怖いけれど「その恐怖こそが祝福につながる」という逆転の発想をしているんです。
これも前述の「恐ろしい存在をただ排除するのではなく、役割を与えて受け入れる」に対応しているイベントってことですね。
ちなみにこのイベントでもたらされる祝福は、「五穀豊穣」「無病息災」ですって。
修行鬼会の合間には人々が鬼を自宅に招いて、酒を酌み交わすことも。
本当の意味での「鬼さんこちら、手のなる方へ」状態ですね。
祭りごとに限らず、くにさきの鬼は人々の生活の中に溶け込んで、日常の中でも“親しみをもって”語られました。地域全体が「鬼と共に生きる」文化圏になったんですね。
そりゃ日本遺産にもなりますわな。オリジナリティ高すぎて。
最後に、くにさきの修行についてまとめます。
鬼たちは確かに日常にも溶け込んでいたんですけどやっぱり本質は”神聖”な鬼です。
鬼は不思議な法力を持つ存在として修行僧の間では捉えられてたんですよ。
なので多くの僧侶がくにさきに修行に出向き、修行僧によって鬼の世界が作られました。
くにさきでは鬼=仏なので仏の世界ですね。
この仏の世界を六郷満山(ろくごうまんざん)っていいます。
より具体的には国東半島全体に広がる寺院群の総称を六郷満山といいます。
ここで修行僧が行った修行は山岳修験と仏教が結びついたような独特な修行でした。
んで鬼は国家安泰から雨乞いまで様々な願いをかなえたと。
日本遺産ストーリーはこんなもんですかね。
似ている世界遺産
今回紹介したくにさき。一般的に恐ろしいものとして伝えられている鬼が”神として”信仰されている。そんな特徴をもつ遺産でしたね。

そこで私が提案する似ている世界遺産はインド・カジュラーホの寺院群です。
カジュラーホの寺院群の特徴は以下の通り。
- ヒンドゥー教とジャイナ教が混在する寺院群
- 中央インド王朝、チャンデーラ朝最盛期に建立
- 25の寺院が現存
カジュラーホの寺院群を歩くと、壁一面に彫られた神々や人々の姿に圧倒されます。破壊と同時に再生を司るシヴァ神、豊穣を象徴する女神、さらには日常や性愛を描いた像まで色んなジャンルの像が並んでいます。
「恐怖と救済」「死と生」「俗と聖」といった対立する要素が、ひとつの空間で共存してるんですよ。これって、くにさきと似ていますよね。
特に、「破壊神シヴァ」が信仰の中心であり、恐怖や死をも象徴する存在でありながら、同時に再生と恵みを与える“救済の神”でもあります。
「一見すると矛盾するものを同時に受け入れる姿勢」は、くにさきの文化と似てますね。
鬼を恐れるのではなく、畏敬し、やがて仏と重ね合わせていった国東半島の人々の心性。そこには、「相反するものを調和させる」という精神性があったといえます。
だからこそ、くにさきが日本遺産に選出されたんでしょうね。
ただし!カジュラーホとくにさきでは決定的に異なる特徴があります。
まぁそれがそれぞれの遺産を遺産足らしめているんですけど。
それは「一見すると矛盾するものを同時に受け入れる姿勢」の向き合い方。
カジュラーホでは芸術として視覚化されたのに対し、くにさきでは祭礼や修行を通じて“体感する信仰”として息づいてきました。このことから、相反するものを受け入れる精神が、世界各地で独自の形をとっていることがわかりますね。
まぁどっちも良い遺産だよねってことです笑。
まとめ
くにさきの日本遺産は、仏と鬼――
本来対立しそうなものを、ひとつとして受け入れた「寛容な文化」の象徴とも言えます。
今でこそ「仏と鬼は別」と思われがちですが、
くにさきでは「どっちもあり」で、それが人々の心のよりどころだったわけです。
そんな「混ざり合った信仰」の世界を今も感じられるのが、くにさきの魅力。
鬼に会いに、仏に触れに、心静かな旅に出てみませんか?
ここまでご覧いただきありがとうございました。またおいでくだされ。